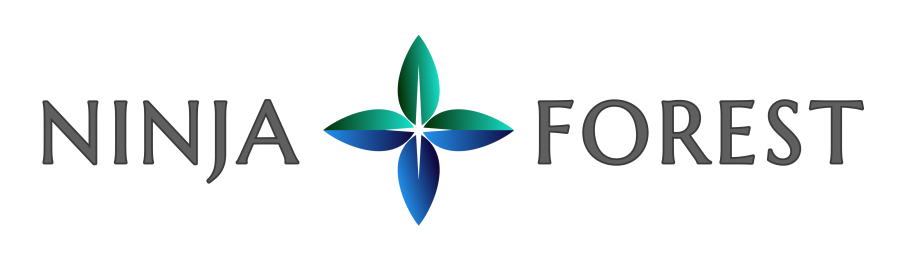見えていなくてもそこにあるもの

忍者はいわゆる陰の存在として知られていますが、一般人に紛れて諜報活動をする方法もあり、表と裏の両方の世界で立ち回りました。さて、日本のみならず、古今東西に諜報活動をする人はいるのに、なぜ今も「NINJA」が国際的に知られる存在なのでしょうか。映画や漫画等の創作コンテンツによる影響も大きいと思いますが、ここでは日本人の独自性と絡め深掘りしてみます。
近年の研究で明らかになったのは、日本古来の忍者の主な使命は「生きて情報を伝える」ことだったということです。長く生き残るには、互いの労力を奪い合う「戦」よりも、有益な情報を持っている方が有利かつ優位なのは明確で、忍者はそのために情報収集をしました。
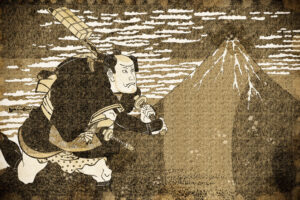
そして勝負の世界で時々言われることですが、「勝ち」を狙っていくのと「負けない」つもりで勝負するのとでは、結果は同じだとしても戦術と精神状態が異なります。
忍者はその「負けない」とほぼ同義の「生き残る」ことが使命だったため、相手方の恨みをかうような戦い方をせず、勝ってその功績を誇示することもありませんでした。相手を叩きのめし、恨みや妬みをかうようなやり方は、負の連鎖を生み命がいくつあっても足りないという経験則と心理的な知見を持っていたからです。
さて、忍者は自らも姿を消すと同時に、視覚的に見えないものも「ある」という前提のもと、それを行動に移す方法として実践していました。その事例として以下があります。
①忍務の前に行う九字護身法(まじないの一種)は、呪文を唱え印を結ぶことで多くの神に護られる、という儀式で、これを経て戦に臨んだと言われています。(ちなみにこれは忍者だけでなく多くの武士も用いたとされています)
②呼吸法を駆使して、それにより気配を消したり、身体や精神状態のコントロールをしました。
無策や神頼みで事に臨むのでなく、「目には見えないが確かにある」力を得て、強い気持ちで行動ができるという経験からこれらを意識的に活用していたのだと思います。後の研究により、九字護身法も呼吸法も明らかに効果を生む因果関係があった、ということが判明しています。

「お天道様が見ている」「八百万の神」「徳を積んだ」などの表現や、今でも「空気を読む」「間を大事に」などの言葉は日常的に使われます。視覚化・数値化はできなくても、何かが存在することを肌で感じる…意識の深いところですでに知っていて、何かとつながっている感覚。これらは、忍者に限らずとも元々日本人の中にある感覚でしょう。そして陰の世界で生きるからこそ、より見えるものが忍者にはあったかもしれません。
このように、勝ちを取りに行くのではなく「負けない」「できるだけ戦わない」ことに重きを置いたり、功績にも名誉にも興味を示さず黙々と仕事をして終われば気配を消してスッと「引く」ような生き方は、日本独自の価値観であり”ユニーク”であるため海外の人にエキゾチックな印象を残し、彼らを惹きつける一因となっているのかもしれないと思います。