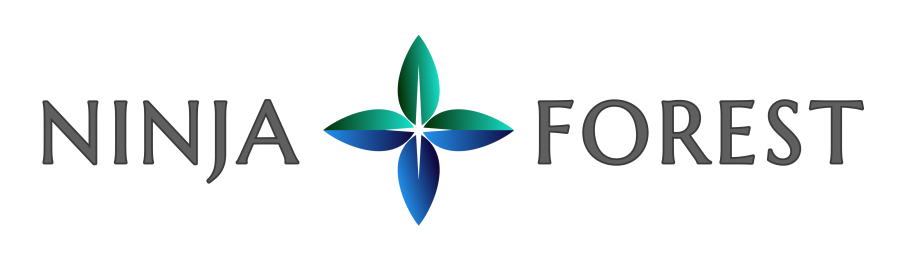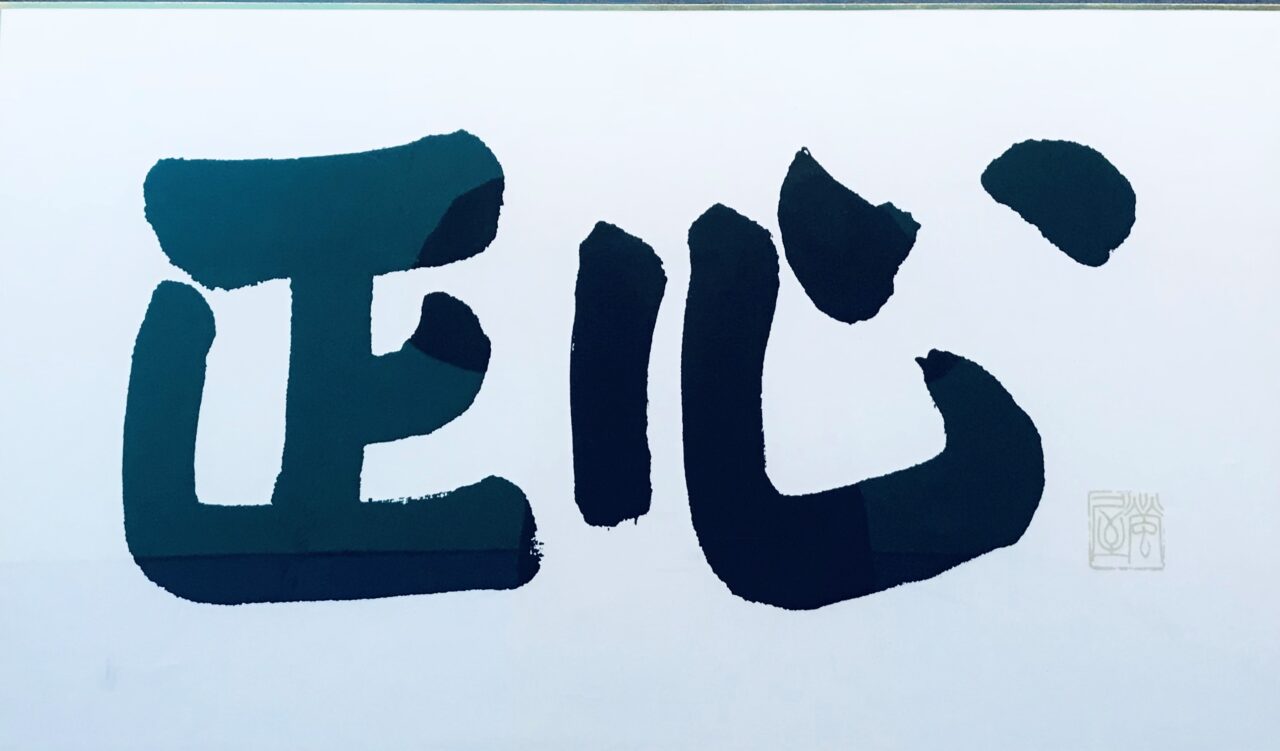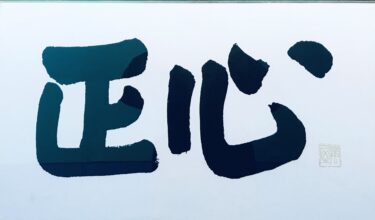正しい心を忘れない
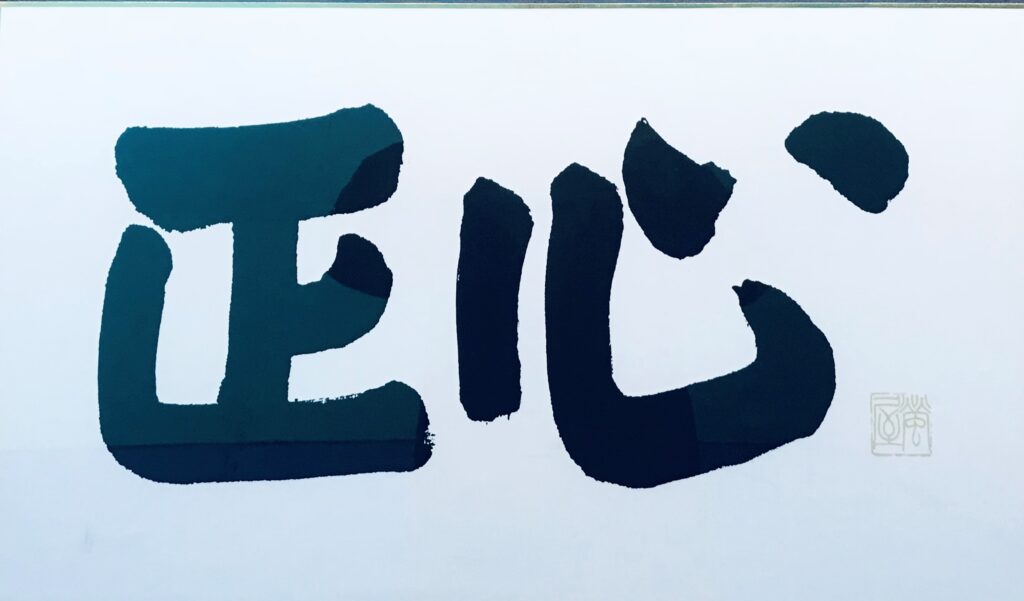
忍術を誤って用いれば盗賊と同じであり、私利私欲のためではなく、大義のために忍術を行うべし。(忍術書・万川集海から引用)
忍者は虚と実を織り混ぜて、家屋のみならず人の心にも忍び込み、火を放って混乱させたり噂を流したりするための、侵入術や心理学に基づく様々な技を持っていました。そんな忍者だからこそ「正心」を忘れないように自らを戒めました。そして、忍者としてその技や能力を私利私欲のために使わないことを固く心に誓いました。
忍者が活躍した戦乱の時代、彼らの目的は「生き残ること」と「有益な情報を得て帰ること」でした。その理由は、情報を効果的に活用して戦うことが、戦による双方の犠牲と、ひいては戦そのものを最小限に留めることにつながるからです。それは紀元前の孫子の兵法にも書かれている、「理想的な」戦い方でした。
さて忍者が戦いに深く関わりながらも必ず生き残るためにはどうするか?それはまず「忍ぶ」ことでした。もし忍者が忍ばずその存在を誇示すれば、必ずや対立する者が現れ、力をぶつけ合うことになったでしょう。(現代でも似たようなことはどこでも起こりますね。)あまりに目立ちすぎると、敵のみならず雇い主からも疎まれかねません。そのような不毛な衝突や危険性を避けるため、陰で活動を続けました。任務を達成することのみに専念して、功績を誇ったり名前を残そうとはしないということです。そうして、武士や侍とは違う形で、忍者は縁の下の力持ちとして土地や城主を支えました。
表で生きた武士と陰で生きた忍者、それぞれが役割を全うし、両輪として機能したことで時代が大きく動いたのです。

「忍」という字は「心」の上に「刃」があることから、(1)移ろいやすい心に刃を置いて常に自らを律した、とか(2)人を傷つける刃を自らの心に置くことで無謀な行動を律した、とか(3)刃を突きつけられるような状況でも心を動かさない不動心を表す、などと言われます。忍者は常に己の心と向き合いながら、地道に泥臭く自らの限界に挑戦し続けました。
そうして、揺れながらも「正しい心」に戻ってこられる精神を持っていたことが、忍者と盗賊との違いだったのではないでしょうか。